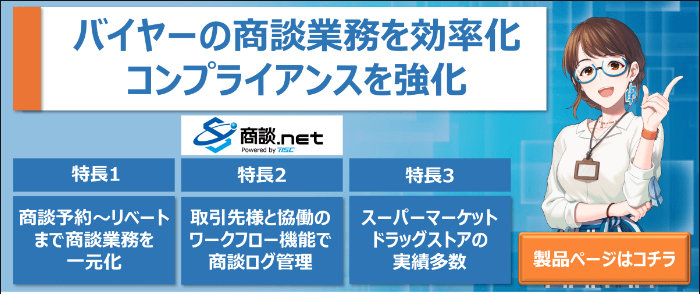小売業のコンプライアンスを高めるクリエイティブラインの業務改革

競合が一層激しくなる中では、サプライチェーンを担うお取引先との改廃を含む適切な取引改善は必要不可欠です。
多くの小売企業は我が国の『失われた30年』における成長のために、IT関連の導入をはじめとして多くの対応をしました。
しかし残念なことに一部のスーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストアを除き、店舗の品種構成は大きく拡大していません。
それ以前、つまり日本の小売業が業種店から業態店へと変化した60年前から30年前の30年間は、ラインロビング(扱い商品群の増加)で成長したのですが、この経験が生かされずに品揃えや品種構成の変化が少なくなり、成長が止まってしまったと言われています。
一方で、我が国で急成長した小売企業は、適切なラインロビング強化を推し進めて、サプライチェーンを大胆に見直しました。
つまり、長く安定した取引実績のあるお取引先だけではラインロビングや社会のサプライズを伴う商品開発は不可能であり、ソーシング活動を活発に行って新たなお取引先を開拓したのです。
新たなお取引先との取引開始は、既存のお取引先との取引の一部または全部を停止しなければなりません。
この際のお取引先との揉め事を回避し、思い掛けない費用と時間を回避するコンプライアンス対策事例を採用して社業を発展させましょう。
目次
小売業におけるコンプライアンスの課題

企業のコンプライアンスは広範囲に亘り対象になりますが、小売業ではお取引先への優越的な地位に因る不正な取引が対象になる可能性が高くなります。
不正な取引とは、契約という形式で事前に締結される、あらかじめ合意された取引条件が事後的に変更される場合とされます。
また、形式的な形さえ整えれば良いといいモノではなく、当事者の実質的な意思が合致している事実が無ければならないとされます。
つまり、取引契約書という文書で表現できる範囲のみならず、途中の経緯も保管・管理されていなければならないのです。
しかし、多くの小売業では契約書やお取引先が提出する商談報告は属人的に保管しており、個別商談の経緯を記録せず、更には相互に合意したと見なされる形式を採用している事例は少ないようです。
また、ドキュメントを組織的に保管していても、承認プロセスが仕組みとして機能していないので後の利用に難渋するといった報告を聞きます。
また、契約書は今もって紙が大半で在り、個別の調査ならまだしも、全般的な締結内容の分析には多大な労力を要することが課題になっています。
他方、各種の取引契約の中でも、リベート関連は実績に与える影響が多いにもかかわらず、お取引先からの入金を検証することなく受け入れています。
達成型リベートを一部のバイヤーやマーチャンダイザーは管理しながら適切な行動をしますが、大半は成り行きに任せています。
このリベートに関する課題認識は低いですが、利益を高めるために合意事項を検証して互いに牽制する姿勢の必要性は高まっています。
もう一つ忘れてはならない事項に、事前に合意した納入価格を下回る発注をしてしまうことが有ります。
ほとんどが商品担当者を始めとした小売側の記入や入力ミスに因るのですが、合意した内容が人の手を経ることなくシステムに反映されれば回避できるのです。入力ミスへの対策を怠れば最悪の場合には不当取引として、コンプライアンスに発展する場合があると認識せざるを得ません。
先に述べた既存のお取引先との取引の一部または全部の停止に際して、稀であると思いたいのですが、お取引先と組織や社員、果ては役員レベルが不適切な関係に発展していると、取引の縮小や停止を察したお取引先が牙を剥き阻止しようとするケースを見聞きします。
公式には不適切な関係を阻止すべく金品の受け取りや供応の禁止などをお取引先に依頼しているにも拘らず、社員が受けてしまうので、管理を強化して不適切な関係の防止を課題と認識する必要が有ります。
長期継続取引で甘くなっていたコンプライアンスは、お取引先改廃の時に厳しく問われるので、なし崩し的に取引継続せざるを得ないのを避けるには、エビデンス等の保管と迅速な提示を可能にする仕組みの導入が必要です。
ところが一方では、コンプライアンスを徹底するための体制強化には労働時間の延長といった新たな問題が発生します。
労働時間を現行以下にしながら、コンプライアンスを強化するという課題を解決しなければなりません。
小売企業経営におけるコンプライアンスのポイント

前段では、小売企業経営において法令もしくは社会規範に違反する確率が高いのは、バイヤーやマーチャンダイザー活動におけるお取引先との接触と合意が市場メカニズムに基づく公正な取引を阻害した時と述べました。
故に、小売企業経営におけるコンプライアンスのポイントの1つ目は、バイヤーやマーチャンダイザーのお取引先接触の可視化対策です。
そして、接触により発生する情報をデータ化して、再利用や検索を容易にする社内共有です。
一方で、コンプライアンスというと順守状況のチェックと言った、どちらかと言えば後ろ向きの行動を思い浮かべることが多いのですが、リベート合意内容の達成状況をチェックし、より多くの収益を得る行動と上長による進捗管理と言った前向きな組織行動が2つ目のポイントです。
3つ目は、情報共有と進捗管理をブツ切りで行うのではなく、フォロー化して一連の流れにする取り組みです。
お取引先との商談は『迎える』から『訪れる』に変える必要性
同質化競争の中で抜きん出る小売業は、扱い商品が来店客の期待する品揃えと価格を良い意味で裏切っています。
そんな光景を間近に見聞きしているにも拘らず品揃えの改廃や定番のディスカウントができないのはソーシング活動が不十分であるからと言われます。お取引先との接触や合意を行う場所が小売業の施設内では、お取引先の「売りたい」品といった矮小化された選択肢から選ぶという悪しき習わしが続いてしまいます。
お取引先の本社に出向けば、全ての扱い品や取り組みの強弱を観察でき、同質化競争から抜け出す品揃えの選択肢を獲得できるのです。
また、バイヤーやマーチャンダイザーが生産現場や物流施設を見学すれば、トレード・オフの気づきと共に価格に関する斬新な条件をひらめく可能性が高まります。
昭和時代の商談効率のために常識化したお取引先を迎えた商談に因る調達を、相手先への訪問による商品調達に変革すれば激化する競争を勝ち抜けます。
バイヤーやマーチャンダイザーはメーカーの改廃や価格変更、特売企画の作成に労働時間の大半を割かざるを得ない現状を打破し、自社施設内に『迎える』与えられる情報収集を止め、ソーシング活動といった『訪れる』事実獲得に脱却して良い意味の異質な品揃えと価格を売場に展開してはいかがでしょうか。
新しいバイヤーやマーチャンダイザー像を支援するシステム

では現時点でも多忙なバイヤーやマーチャンダイザーが、『迎える』商談の時間調整等から解放され、『訪れる』ための業務や作業見直しはどうすれば良いのでしょうか。
直ぐに思いつくのは現行作業を効率化して作業時間を作る方法ですが、“効率化”と聞くと多くの方は“単位作業の所要時間を短縮する”と解釈すると思いますが、経験法則に照らすと所用時間の短縮は低効果です。
効率化とは“現行の単位作業を止める”方が高い効果が有ります。
つまり、バイヤーやマーチャンダイザーが自社内で行っている作業を無くすのが重要です。
バイヤーやマーチャンダイザーは定番商品改廃と特売企画が主な業務ですので、商談が大きなウェートを占めています。
商談の依頼や面談日時の調整をシステム化の上で自動化すれば大幅な作業時間の短縮になります。
また、商談そのものをWebで行い録画保管する、商談記録をお取引先セールスにお願いして電子資料で入手し保管する、合意文書としての契約書を電子化されたものに変更して安全に保管すると言った業務改革を行えばコンプライアンスレベルも高まります。
更に、お取引先との接触状況が共有できれば、商品部門のマネージャーや統括している役員が進捗や内容に関して、適時適切なフォローを入れることができて、信用度向上に対する効果も期待できます。
この様に商談におけるIT利用が進めば、自社内で商談しなくても良く、ソーシング活動の移動や隙間時間にどこででも商談ができるので内容の濃い活動が可能になります。
今までの小売業のIT化対象は受発注やPOSとCRM、買掛管理や成績管理でしたが、今後はバイヤーやマーチャンダイザー業務にも広げ、クリエイティブラインのメンバーの労働生産性を上げなくてはならなくなっています。
【参考】ECRはメリットが多いの?背景と現状を小売視点で解説
【まとめ】小売業のコンプライアンスを高めるクリエイティブラインの業務改革
「小売業のコンプライアンスを高めるクリエイティブラインの業務改革」というお題でご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今年に入ってからも、公正取引委員会より、スーパーマーケットや家電量販店などの小売業における取引先への不適切な対応についての発表がありました。
さらに今後もコンプライアンスの意識が増すことが予想されます。
弊社でご提供しているバイヤー向け商談システム「商談.net」は、小売業とお取引先様が協働して、商談業務の省力化と一元化を図るシステムです。商談内容の履歴や書類を残すことで、コンプライアンス強化を図ることが可能です。
また、リベート管理システムは、小売業様のリベート管理を一元管理し、達成や入金管理を強化しております。
よろしければ、製品資料もありますのでぜひご覧ください。
著者:株式会社テスク
愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企業様に導入されており、これまでに蓄積したノウハウを活かして、流通業の業務改善や経営課題の解決を支援しています。