小売業向け基幹MDシステムとは?刷新の選び方や選定基準をご紹介!

小売業においては、商品管理、在庫管理、店舗端末、分析機能、POSシステムの連携などの小売業のマネジメントサイクルとMD(マーチャンダイジングサイクル)MDを網羅した機能を提供する、小売業向けの基幹システムが必要不可欠です。
また、導入後も現場で最大限に活用されなければなりません。
一方で、ご理解はいただいたいるものの、このような疑問や課題をお持ちではないでしょうか?
- 小売業の基幹システムの全体的な概要をおさらいしたい
- 小売業の基幹システムで必要な機能を知りたい
- 小売業の基幹システムのベンダーやパッケージを選定する上で何を重要視するか知りたい
本コラムでは、小売業基幹MDシステムの全体概要をお伝えしつつ、求められる機能や選び方のポイントをわかりやすくご紹介します。
目次
小売業向け基幹MD(マーチャンダイジング)システムとは?

基幹MDシステムとは、小売業のマーチャンダイジングを支援するシステムです。
以下のニーズを満たしているシステムがMDシステム(マーチャンダイジング)となります。
- 消費者ニーズに沿った商品を探せる
- 消費者ニーズに沿った商品を適正価格で提供できる
- 消費者ニーズに沿った商品を適切な数量調達できる
- 消費者ニーズに沿った商品を適切なタイミングで提供できる
では、小売業向け基幹MDシステムに求められる機能とはどんな機能か、そして選定ポイントは何でしょうか?
必要機能1:部門管理機能
小売業(チェーンストア)は、店・部門に分けた運用が行われており、それぞれ店や部にご担当者様が配置されます。
そのため、MDシステムには「部門管理」の機能が求められ、それにより各店・部門の実態を把握しながら経営できるようになります。
必要機能2:商品管理機能(マスタ管理)
小売業は消費者のニーズに沿った商品の品揃えを行うため、商品を管理する機能が必要です。
商品の管理には、商品の概要・商品の特性など商品自体の情報、通常売価・特売売価などの販売価格の情報、その他にPOPなどの販促活動のために必要な情報など、様々な情報を管理することで効率的な商品管理を実現できます。
必要機能3:POSとの連携機能
POSシステムは、多くの消費者の購買を効率的に行うために必要な機器となっています。
そのため、POSへの商品概要情報・商品価格情報の配信と、POSシステムで収集した販売情報の集信を行う機能が求められます。
必要機能4:補充発注機能
棚に商品が並んでいないと当たり前の話ですが消費者は購入しません。
そのため、効率的に補充発注できる機能が求められます。
必要機能5:その他機能
小売業は、POSの他にも、計量器・POPソフト・棚割ソフトなど、多くのシステムから成り立ちます。
基幹MDシステムは、各ソフトと連携し、全体効率を図るためにシステムのHUBの役割が求められることがあります。
上記の機能が備わり、チェーンストアの基礎に連動し、基本業務を確実に実施できるかが大きなポイントです。
また、特売などのマーケティング企画を管理できるかどうかも重要な要素となります。
小売業向け基幹MDシステムとは?「販売管理」

販売管理システムとは、日本では、商品販売に関する情報を管理するシステムを指すことが一般的でしょう。
企業は商品などを販売した際、様々な管理を行わなければなりません。
- どこに販売したか
- 何を販売したか
- いくらで販売したか
- 代金の回収はいつ行うか
など、たくさんの情報を管理するシステムが販売管理システムです。
では、小売業向け基幹MDシステム「販売管理」に求められる機能とはどんな機能か、そしてポイントは何でしょうか?
販売管理①:商流管理機能
多くの企業は物品やサービスの販売業務を営んでいます。
それらの販売業務、いわゆる受注や売上といった商流の管理を効率的に行う機能が求められます。
また、物品やサービスの販売を行うために購買業務を営んでいますが、それらの購買業務、いわゆる発注や仕入といった業務の管理を行う機能が求められます。
販売管理②:物流管理機能
物品の取扱いをしている企業は、物を自社まで持ってきてもらうことや物を購入頂いたところへ持っていくことを行う、いわゆる物流業務を営んでいます。
入荷・入庫・出荷・出庫・在庫管理・棚卸などの業務がこれに該当し、効率的に行う機能が求められます。
販売管理③:金流管理機能
商流は契約内容の履行により完結しますが、それに伴い金銭のやり取りが発生します。
それら金流業務、いわゆる売掛・請求・入金・買掛・支払などの業務を効率的に行う機能が求められます。
販売管理のポイント
基幹MDシステムにおける販売管理のポイントは、主に以下になります。
- 標準的な業務フローを有しているか
- 各業務が有機的に連動し、かつ、業務効率化を支援するか
- 業界特有の商習慣への対応を支援できるか
- 長期利用を行うことが前提となったシステムか
- 柔軟性・拡張性の優れたシステムか
昨今は、販売管理システムを有効活用することで企業活動を効率的に行っています。
上記以外にも、例えば、統合性や信頼性などの要素があるかどうかも重要な要素となります。
小売業向け基幹MDシステムとは?「在庫管理」
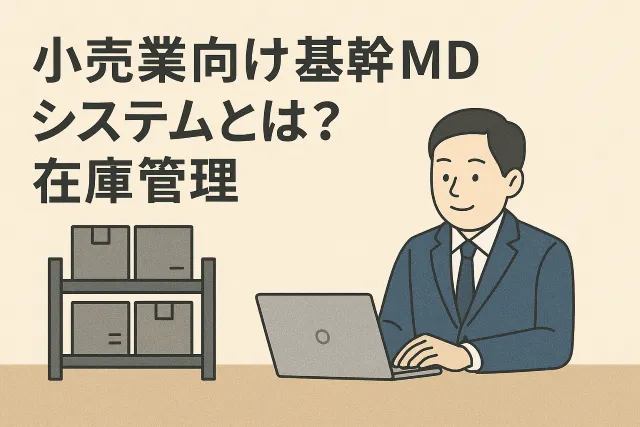
在庫管理システムとは、販売管理・物流管理と密接に関連し、モノの動きを管理していく役割をもっています。
- 現在どれだけの在庫があるのか?
- それらの在庫の金額はいくらなのか?
- 在庫の受払いはどう動いているのか?
などのたくさんの商品情報を管理するシステムが在庫管理システムです。
では、小売業向け基幹MDシステム「在庫管理」に求められる機能とはどんな機能か、そして選定ポイントは何でしょうか?
在庫管理①:在庫数量管理機能
在庫を持たずに業務運営されているサービス企業などを除けば、ほぼ全ての企業で在庫を抱えています。
現状、在庫数量がいくつあるのか?それを管理する機能が求められます。
リアルタイム性があるばかりでなく、数量異常が分かるような工夫も同時に求められます。
在庫管理②:在庫金額管理機能
財務会計で必要となる、棚卸資産の算出も在庫管理に求められる機能です。
棚卸を実施し、自社で採用している棚卸資産評価法に基づいて算出します。
在庫管理③:在庫受払管理機能
いわゆる在庫がどのように動いたのかのログの機能です。
受払いといわれる事も多く、どこから入って(入荷)どこへ出て行った(出荷)のか?
また、廃棄や社内利用で出庫したのか、はたまた調整のため入庫されたのかが分かるような機能が求められます。
在庫管理のポイント
基幹MDシステムにおける在庫管理のポイントは、主に以下になります。
- 販売管理システムと有機的に連動し、かつ、業務効率化を支援するか
- 在庫数量と金額の双方を管理できるか
- 在庫の受払いの管理ができるか
- 在庫の倉庫間移動を効率的に支援できるか
- 棚卸業務を効率的に支援できるか
- 物流マテハンとの連携容易性が担保されているか
- 業界特有の特殊な預り・預け・委託などに対応できるか
- リアルタイム性が担保されているか
昨今は上記以外にも、賞味期限別の管理ができるかなど、在庫管理機能に求められる機能が増えてきています。
自社が何を求めているのかを明確にし、それに合致するシステムを選定するのが重要になります。
小売業向け基幹MDシステムとは?「データ分析」

データ分析とは、MDシステムで集めた部門実績や単品実績、販売管理システムで集めた得意先や商品毎の実績データを経営判断できるよう見せ方を加工し、売上・利益などの向上の為にデータを可視化するシステムです。
では、小売業向け基幹MDシステム「データ分析」に求められる機能とはどんな機能とポイントは何でしょうか?
分析管理①:現状を把握する分析機能
現状を把握できる分析として、例えば、売上の分析、粗利(荒利)の分析などがあります。
その他、自社が取り扱っている商品についての分析も求められます。
分析管理②:業種業界向けの分析機能
チェーンストア様では部門分析・単品分析・時間帯分析などが求められます。
卸売業様・メーカー様では、得意先分析・商品分析・組織別分析などが求められます。
業種業界によって、管理の仕方が違いますので、それに沿った分析が求められます。
分析管理③:応用的な分析機能
応用的な分析として、多種多様な分析手法が世の中には存在します。
それらができるような分析機能を有しているか?
また、自社にとって有益な分析なのかどうかを見極めた上で、必要に応じた分析機能が求められます。
分析管理のポイント
データ分析システムを選定する時のポイントは、主に以下になります。
- 業種・業界によって、見たいデータが変わるため、自社にマッチしたデータ分析システムか?
- データの見せ方に工夫があり、アクションに繋がる分析システムか?
- 自社でデータの抽出が自由に、もしくは容易に行えるか?
- 画面上での照会の他、CSV出力や紙への出力などがしやすくなっているか?
- データ抽出までの時間(レスポンスタイム)は許容できるか?
昨今はAIやビッグデータを利用する方向へ向かっています。
上記において、自由度・柔軟性・早いレスポンスが特に重要となっています。
小売業向け基幹MDシステムとは?「自動発注」

自動発注システムとは、最適な在庫となるよう自動で発注データを作成し、発注業務の効率化を支援するシステムです。
- どのような発注方式を採用するかを設定
- 自動発注を行うアイテムを設定
- 計算式による発注数の算出
などのたくさんの発注情報を管理するシステムが自動発注システムです。
では、小売業向け基幹DMシステム「自動発注システム」に求められる機能とはどんな機能か、そしてポイントは何でしょうか?
自動発注①:発注数算出機能
発注数を算出する計算式は多種多様なものがあります。
商品の特性や店舗・企業の特性に合わせて計算式を選べる機能が求められます。
自動発注②:発注タイミング設定機能
発注のタイミングは、取引先様が関係し、納品までのリードタイムも関係するため、適正なタイミングで発注を行う必要があります。
発注してから物が届くまでに欠品が発生しないよう、また過剰在庫にならないよう支援する機能が求められます。
自動発注③:発注数量補正機能
商品は、特売や地域イベント、またTVなどのメディアの影響で爆発的に売れる場合があります。
そのようなイレギュラーな販売数量は、その特性を見て排除しながら発注数を算出する必要があります。
そのため、発注数量を補正する機能が必要となり、該当機能がない場合、発注数が過大になりやすい特性があります。
自動発注のポイント
自動発注システムを選定する時のポイントは、主に以下になります。
- 商品特性に応じて発注方式を選択できるか
- 納品リードタイムを利用し、発注数と発注タイミングを算定できるか
- MDシステムや販売管理システムと有機的に連携しているか
- イレギュラーな販売数量を排除する仕組みがあるか
- 自社の管理レベルに沿った機能を有しているか
自動発注システムを導入し効果を上げるためには、単品在庫管理の運用が適切にされているいかが重要です。
また、発注を流通BMSや自動FAXで送る仕組みが存在しているかが重要な要素となります。
それらがまだ整備されていない場合、算出された発注数量は使えない場合が多く、また発注作業の自動化ができないため、結果として効率化が行えません。
自動発注を行う前提条件が整っている場合に限り、最大の効果があがるのが自動発注システムの特性です。
「自動発注システム」の導入効果とは?
自動発注システムで発注業務の効率化と在庫適正化を図れます。しかし導入効果は本当に出るのでしょうか。
自動発注システムを導入することで、確かに、発注業務の効率化と在庫適正化を図る事ができ効果はでます。
しかし、そのためには以下4つの前提条件があります。
【前提条件1】 単品在庫管理ができている
自動で発注を流すわけなので、単品レベルで在庫管理ができていなければ効果はでません。
単在庫管理がしっかり出来ていることが前提となります。
【前提条件2】 運用が徹底できている
在庫に関わる部分としては、例えば、仕入伝票の登録遅れなどがあります。
仕入伝票を現場の方が握りしめ処理されない状況になっていると、在庫が不正確になり、必要ないのに発注するなどのケースに繋がることなどがあります。
また、棚卸の精度も重要になります。
現場のご担当者にこのあたりの教育が行き届き、しっかり運用できている事が前提となります。
【前提条件3】 小さく初めて範囲を広げていく
最初から対象商品を広げすぎると、その発注がうまくいっているかどうかチェックできなくなります。
よって、小さく初めて徐々に対象を広げていくようにする事が重要です。
【前提条件4】 自動発注を始める時の初期設定値が重要
自動発注を始める時、商品毎に、安全在庫・最大在庫・発注点を決める必要があります。
自動発注システムの中で、その在庫設定値は自動補正していくとしても、初期値だけは誰かが決めなければいけません。
その初期値がおかしいと、自動発注が最初うまく回らず、混乱することになります。
誰がするのが適正なのかと考えると、おそらくバイヤー様が一番しっかりとした設定ができると考えられます。
【参考】基幹システムでIT戦略を成功させる方法とは?効果を上げるための解決策をご提示
小売業向け基幹システム・ベンダーの選び方・選定基準

小売業で基幹システムのベンダーを選定する際は、個別事情によって重み付けは変わりますが、判断の基準と優先順位はある程度一般化できます。
以下では、目的→会社(ベンダー)→導入時→導入後→費用の順に観点を整理し、評価の勘所を記載します。
これらによりRFP(提案依頼書)作成やベンダーの選定の際の基準として活用できます。
選び方1. 目的の実現度(プロジェクトで実現したいこと・目指す姿を言語化する)
最上位の評価軸は「目的の実現度」です。
売上や荒利の改善、在庫最適化、業務標準化、属人化の解消、内部統制強化、売上・店舗拡大への対応など、狙う成果を明確にし、定量面もしく定性面で言語化します。
その成果を得るためのツールとして基幹MDシステムが役立ちそうかを見ます。
加えて、スコープ(基幹システムで担う範囲、周辺システムとの役割分担)を決め、目的を満たすための全体構成となるようにします。
選び方2. システムベンダーの小売業における導入実績と在籍SEの質
基幹システムのリプレイスをお願いするシステムベンダーが、どんな実績と体制で開発・導入・サポートしているかが重要な要素となります。
詳細をみていきます。
2-1. 小売業での導入実績
小売業の業務運用やシステムは独自である要件が多く、そのため他業種での実績はあまり参考になりません。
同等規模・同業態での事例数と質を確認します。
また、単なる導入数ではなく、「稼働後の効果」「定着までの期間」「ユーザー満足度」等を具体的に聞き取り、担当予定のPM/SEの経験値も重視します。
2-2. SE(システムエンジニア)の質と層の厚さ
エンジニアとしてのシステム面の力量だけでなく、小売業の業務を理解した業務面での知識も必要とされ、小売業の業務エンジニアは希少です。
また、基幹は長期利用が前提。その層の厚さも含めて求められます。
開発・保守を担うエンジニアのスキル、レビュー体制、ドキュメント整備、テスト計画や実施の成熟度、ナレッジ共有、新人や若手エンジニア育成体制の仕組みを確認します。
属人的な特定のエンジニア依存は、長期的にはリスクです。
2-3. 企業の継続性・長期的なサポート
財務健全性や利益率、製品バージョンアップ方針、事業ポートフォリオの安定性、経営者の長期的視点など、中長期で伴走できるかを評価します。
金融やメーカーなど他業種と比べて小売業では主要基幹システムパッケージや主要ベンダーの撤退などが比較的起きやすく、これらの情報から長期的に提供が可能かどうかをユーザー側でも判断する必要があります。
2-4. 営業の小売業の理解や取り組み姿勢
基幹システムの入れ替え目的を実現するパートナーであるベンダーの営業も重要です。
入れ替え目的によりますが、近年の小売業のシステム導入はシステムだけでなく業務の大きな変更を伴うことが多く、社内のユーザー部門や経営層の理解を必要とします。
自社の業務・特徴・課題・組織体制を理解した上で、システム活用のための社内のネゴシエーションの進め方のヒントやアイデアを提供できるかどうかは大きなポイントです。
選び方3:適合度・拡張性・連携性・体制・ノウハウ
続いて、プロジェクト導入時のポイントも重要な要素です。
3-1. パッケージ適合度と機能拡張性
パッケージの資料やデモでの説明を聞き、標準機能でどこまで合うかと、差分はアドオン開発できるか、そのような事例や開発体制があるか、を評価します。
ベンダーはターゲット企業の50%以上のニーズがある場合はパッケージ機能として実装しますが、20-30%以下の場合は事例としてパッケージ化しないケースがあります。そのような事例を多く持っているかどうかも確認しましょう。
また、帳票システムなど、企業固有のものが必要な要件が生じる領域については設定や簡単な開発で行えるかどうかも評価すべきです。
3-2. 周辺システムとの連携性
小売業の基幹システムの基本機能は、商品マスター・仕入データ・販売データ・店舗データなどほぼ全てのデータが蓄積します。
今後、生成AIを通じた周辺システムが開発されていくと考えられますが、基幹システムはその際に重要なデータベースの機能を担います。
そのため、基幹システムやベンダーに周辺システムとの連携性があるかどうかについては確認が必要です。
データベースを公開しているか、他ベンダー製品をOKとしているか、多くの連携実績があるかどうかがポイントです。
3-3. 担当PM/SEの経験とスキル
小売業での業務は他の業界に比べて特徴的です。
導入を率いるPM/SEが同規模・同業の経験や、小売業の業務や小売業のシステムの知識を持っているか、コミュニケーションがとれそうかも評価のポイントです。
評価するためにPMに会って力量を確認することが思いつきますが、優秀なPMほど実際のプロジェクト導入作業で忙しく、営業同行やその準備をするのが難しいです。
最低限これまでのプロジェクト経歴や特徴について営業を通じて確認しましょう。
3-4. 小売業における導入プロジェクトのノウハウ
小売業に限らず基幹システム導入については多くのリスクが伴い、時折ニュースでも取り上げられます。
日経コンピュータでも「動かないコンピュータ」という連載記事もあるくらいです。
特に小売業では店舗も含めると運用に関わる人数が多く、システムトラブルの影響が大きくなります。
そのような導入リスクを認識し、回避のための対策を立てられるか、それを実行できるかについても評価ポイントです。
要件定義における進め方が属人的でなく仕組み化されているか、意思決定がスムーズにできそうかどうか、テストの進め方やユーザー教育が考えられているか、等もポイントです。
提案時には機能面の課題への提案だけでなく導入面での課題への提案を受けましょう。
注意点はプロジェクト失敗の原因はユーザーにあることも多く、そのような「耳の痛い事実」を指摘するベンダーの評価を下げないようにすることです。
選び方4. 導入後における保守の充実度・バージョンアップ・システム活用支援
最後に、導入後のサポート体制についても考慮しなければなりません。
支援面で重要な要素を紹介します。
4-1. 保守サポート
小売業の多くは土日祝日含めて営業しています。
また店舗が24時間営業していなくとも、基幹システムの日次処理は夜間に実施されます。自動発注などシステム範囲が拡大する中で近年の小売業のシステム対応は24時間365日サポートが求められています。
一言で24/365対応と言っても、夜間にトラブルの受付対応だけ行うベンダーもあり、その内容にも確認が必要です。
そのような対応が取れない場合は小売業での自社の体制の強化を代替策として講じる必要があります。
4-2. パッケージの機能バージョンアップ
近年、小売業では軽減税率・インボイス制度など法令対応のためにシステムの改修が求められるケースがありました。
今後もそのような対応が迫られる可能性もあります。
また、システムは日進月歩であり、長期間利用する基幹システムはどうしても長期利用とともに陳腐化の課題を抱えます。
そのため、ベンダーが定期的にパッケージのバージョンアップを提供するかどうか、そのバージョンアップへの費用が少ないか、については評価のポイントです。
4-3. 継続的な改善・追加導入フォロー
導入目的の達成には、時間を要する場合もあります。
さらに、一度目的を実現できたとしても、人の異動や体制の変化などによって継続性が損なわれ、徹底できなくなるケースもあります。
また、新たな課題が生じ、その解決を求められることも少なくありません。
そのため、ベンダーが入れっぱなしでなく、カスタマーサクセス部などによる定期的にフォローするかどうか、追加導入指導が提供されるかどうかについても確認が必要です。
選び方5. 費用が安いだけではなく妥当性と将来費も見る
初期費用と、ランニング費用での見積で一見数字はわかりやすいですが、ここでも注意が必要です。
まず、ベンダー選定時の多くで「要件定義は確定見積もり、設計以降は概算費用での見積もり」です。
ベンダーによっては概算費用を低めに見積もったり、あえて要件を想定せずに見積もるケースがあります。
誠実なベンダーかどうかは確認すべきポイントです。また、ランニング費用にどこまで含まれるかも確認ポイントです。
サーバ更新時の費用やバージョンアップ時の費用については明記されていないケースが多く、5年後に費用負担が発生する場合もあります。
また、定期的なサポート打合せ、追加導入指導についても料金を確認しましょう。
小売業の基幹システムは、会社の基盤です。
その基盤を支えるシステム選定の成否は、個々の機能比較ではなく「目的に対する実現度」を「長期運用を支える会社と体制か」「パッケージ適合度と拡張性・導入体制とノウハウ」「「導入後の進化力」「妥当なトータルコスト」という本質的な視点でとらえ、選定できるかにかかっています。
RFPやベンダー比較表は、上記観点を評価軸として、幅広くベンダーの情報提供を求め、それぞれの企業の考え方によって重みづけを行って判断することがおすすめです。
【関連】小売業が基幹システムの入れ替えに失敗しない3つのポイント
よくあるご質問
小売業向け基幹システムとは?
小売業向け基幹システムとは、販売管理・在庫管理・発注・仕入れ・買掛・支払・顧客管理・POS連携など、小売業のMD(マーチャンダイジング)となる業務を効率化・自動化するためのITシステムです。
基幹システムをリプレイスする目的を明確化する際、どのような要素を重視すべきですか?
以下の4つの観点を明確にすることが重要です。
・ベンダーの信頼性:小売業での導入実績、SEの質と体制、企業の継続性を確認。
・導入時の適合性:パッケージの適合度、拡張性、連携性、担当者の経験を評価。
・導入後のサポート:保守対応、バージョンアップ、改善フォローの充実度を重視。
・コスト妥当性:初期費用だけでなく、運用・将来コストも含めて総合判断。
まとめ:流通業に詳しい「話せるベンダー」に小売業向け基幹MDシステムを任せたい
業務に明るい営業・システムエンジニアは、市場では意外にも枯渇しています。
守備範囲の広いシステムベンダーや、会社にやってきたシステムエンジニアに、⼀から業務を教える・・・という事に疲れている⽅もいらっしゃるのではないでしょうか。
量販型小売業(チェーンストア)や、消費財の卸売業・メーカーに特化している「話せるベンダー」と組むことはとても重要です。
株式会社テスクは、基幹業務という難易度の高い領域に特化し、流通業のお客様と共にノウハウを蓄積し、業務に明るい人材を抱えており、小売業向け基幹システム「CHAINS Z」を提供しております。興味がありましたら、ぜひ製品資料をダウンロードいただくか、お問い合わせフォームにお気軽にご連絡ください。
最後に、流通業の現場で活用される機能や運用を提供し、小売業向け基幹MDシステムを任せられるベンダーを選びましょう。
著者:株式会社テスク
愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企業様に導入されており、これまでに蓄積したノウハウを活かして、流通業の業務改善や経営課題の解決を支援しています。

