小売業における需要予測の活用!AIやシステムの活用事例を紹介
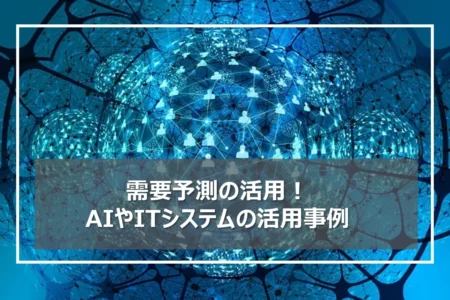
小売業におけるシステム化は、ノウハウ(know-how)のハウ部分、言い替えれば“進め方や手順”分野の一部若しくは全部の運用をITに担わせてきたのですが、AIによりノウ部分、言い替えれば技術や知見を人から剥奪して、ITに対応させるのが可能になっています。
特に、小売業の最重要な行為である『販売』は、需要に対する供給の最適化が成否を決するので、経験と知識を持つスペシャリストが予測する需要に基づく発注が重要視され、スペシャリストの役割をAIに置き換えようとしています。
ところが一方で、優秀なスタッフが居てもその知見が結果を伴うようにするには進め方や手順が整備され、期待通りに“できてしまう”組織や仕組みのモデル構築を必要とします。
小売業は疎かにしがちですが、工業化(Industrialism)計測化(Engineering)単純化(Simplification)を業務に組み込むべきです。
つまり、工業化を導入して計測化を応用し、単純化を実現するのです。
この実現のために、AIを積極的に利用するIT導入を進めるのを目標にすれば、闇雲なAI導入が無意味な投資になるのを防止できます。
小売業にとって重要な点は、AIを利用した需要予測のアルゴリズムを理解する点=ノウに関しては、ブラック・ボックスとしてIT企業や担当者に任せても良く、効果を上げるハウ部分の作り上げ、在庫管理や発注等の商品作業改善に注力すべきであると考えます。
需要予測の活用前に解消すべき小売業の課題とは

需要予測をツール化して発注を支援させるには、レジ等で発生する顧客購買実績等過去のビッグデータを分析させ、統計などの客観的な根拠を基に商品毎の適切な発注日と発注数を立案させます。
この際に忘れてはならないのは、単なる売場欠品防止のみの追求では無く、コストの削減が同時に追求されなければならない点です。
また、小売業の多くは多店舗展開をしているので、各店舗のビッグデータが一定レベルに蓄積されるまで各店舗の精度が高まらないのは問題であり、需要予測を利活用する『御利益(ごりやく)』を得るまでに多くの時間を割かなければなりません。
『御利益』の享受を最短にするには、他店のビッグデータを利用できれば良いのです。
店舗を標準化すれば、客数も近似値になり、店舗作業の標準化も実現させやすいので収益構造も同様になります。
つまり、標準化された店舗であれば、需要予測が流用できるのみならず、商品作業も類似しているので、結果の予測も容易になり、売場欠品防止と収益の向上の両方を短期に獲得できるようになります。
言うまでもなく、ビッグデータを利用したアルゴリズムから得る結果は“類似”サンプル数が多いほど精度が増すので、全店で自動発注が稼働した後も一層“儲かってしまう”需要予測の利活用に磨きがかかります。
ゆえに、需要予測を利活用する前に解消すべき課題は、単純化(simplification)のみならず、標準化(standardization)及び徹底化(specialization)の更なる進化です。
需要予測のメリットは発注精度向上と在庫適正化

小売業は、大別して売場在庫の販売とネット等からの注文販売の二通りがあります。
(訪問販売も類型としてありますが、適正性問題に対する多くの規制が掛かるので解説対象から外します。)
注文販売のシェアは徐々に伸びていますが、諸種の優位性から圧倒的に売場在庫販売が多いのが実情です。
一方で、売場在庫販売は『在庫』が無ければ販売できないといった宿命が有ります。
したがって、『店頭在庫を切らさない』のが販売における最重要な点であり、小売業の日常オペレーションやシステムは、在庫補充のためにあると言っても過言ではないでしょう。
需要予測も目的は”在庫適正化”であり、その手段として精度の高い発注に利用します。
小売業に限らず手段と目的を取り違えて失敗するケースがあるので、この点には注意します。
この「取り違え注意」を喚起するのは、適正在庫が目的であるというには在庫が数値計算により求める仕組みの存在が前提であるのを忘れてはならないからです。
グロサリーは、おおむね需要予測精度が増すと、発注精度が向上して在庫の適正化が実現しやすいですが、生鮮品は原体と売体が相違しているので、青果の様に品目単位の数値換算を利用します。
しかし、惣菜は需要予測の精度が上がっても、収益向上と連動しない場合があり、単なる見込み生産の一助程度と見做して利用するのを忘れてはならないのです。
また、需要に則した商品補充と在庫がコストを極端に押し上げてしまう場合があるのを忘れてはなりません。
例えば、時々発生するイレギュラーな購買に対して、安全在庫を設定して売場欠品がないようにしますが、在庫効率を偏重すると売場欠品を許容してしまいます。
この際に発生するのが来店顧客の抱く“不信”であり、最悪の場合には競合店にシフトチェンジされかねません。
他には在庫効率を極めると極端な多頻度少量発注になり、社内外の物流コストが増加するのみならず、店内物流=商品作業の頻度増加は店舗人件費の増大に繋がります。
需要予測に読み込むビッグデータにはこれらのパラメータを入れなければなりません。
需要予測はビッグデータを学習するAIを利用する

需要予測に限らずAIを利用するには、ビッグデータを学習させなければなりませんが、読者も感じているように、単なるPOS実績やEDIの結果データでは表面的な結果しか得ることができず、適正在庫という目標を達成できないケースを見聞きします。
この際に参考になるのがSCM(サプライ・チェーン・マネジメント)の取り組みです。
SCMとAI需要予測の組み合わせは唐突に聞こえますが、SCMの成果ではなく、SCMが機能しなかった原因を分析し、これを補うデータをビッグデータに組み込めば需要予測の精度が向上すると推察します。
SCMと言えば、商品に対する大量の実績と特性等の深い知見を持つメーカーやベンダーの専門家がカテゴリーキャプテンを担い、小売業側のカテゴリー担当者に助言をして商品補充するといったプロセス(CPFR=コラボレーション・プランニング・フォーキャスティング・リプレニッシュメント)を行います。
しかし、大量のデータと深い知見を持つメンバーが連携しながら、期待通りに機能しなかったケースがあります。
原因を分析すると、
(1)メーカーやベンダーのメンバーには商品=単品という強い意識があるが、小売業のスタッフが持っている品目という概念がないので、単品に振り回されてしまう
(2)また、売れ筋の特徴を知ろうとしないので、重複品目増加に繋げてしまった
(3)売れ筋を捕捉しても、ベンダーの供給不能で連続補充が不能になった
(4)共同で計画立案してもベンダーやメーカーの供給体制にフィードバックされず、継続販売体制構築に生かされない
といった課題への的確な対処が必要だったのです。
これらの教訓を克服するのが、需要予測を活用するには欠かせません。
【関連】小売業での生成AI活用法 ~生成AIが変える未来の小売業業務とは?
需要予測システムの活用事例

現状の小売業では、需要予測をシステム化して活用しているのは、主に自動発注です。
需要予測を利用しない自動発注には売上型(セルワン・バイワン型)=売れた数量分を発注する方式、在庫補充型=在庫数変動行為(売上、移動、廃棄)を在庫数に加減算して在庫の理論値を算出し、基準値(発注点)を下回った商品の必要在庫数を超える数量を発注する方式があります。
そして需要予測を採用した時には、主に売上型に近い方式、つまり需要予測数量を発注する方式になります。
ところが、自動発注方式の経験法則によれば売上方式は在庫補充方式に比べて機能が劣っています。
この実態から導き出されるのは、小売業の3S(Simplification単純化、Standardization標準化、Specialization徹底したことによる卓越化)を理解した上の豊富な自動発注に関する経験と実績が、需要予測の利活用には必須であることです。
【まとめ】
本ブログでは、小売業における需要予測についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
テスクは、小売業様の効率的なオペ―レーションに関するノウハウを持っています。
小売業向け基幹システム「CHAINS Z」は、複合型、在庫補充型更やPI値型自動発注などの多種豊富な導入実績を持つの提供を通じて需要予測の活用に貢献できますので、ぜひ製品ページもご覧ください。
著者:株式会社テスク
愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企

