売価還元法でスーパーマーケットが儲かる?計算式や事例を紹介!
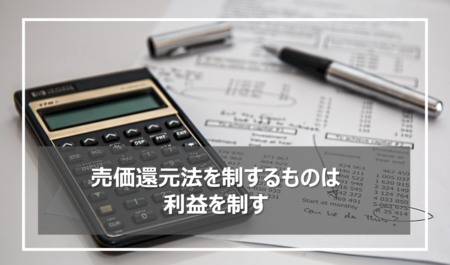
日本のスーパーマーケット上位10社の内で、企業業績が閲覧可能な上場企業は7社であり、その7社すべてが棚卸資産(一部企業は生鮮食品を除く)の在庫評価法には売価還元法を利用しています。
上場企業とは株式公開企業であり、税法のみならず商法の基準を満たさなければなりません。
7社においても生鮮食品や原材料、仕掛品には最終仕入原価法で在庫評価をしています。
生鮮以外の商品を最終仕入原価法で評価するのを認められないといった事情はあるのですが、単に上場基準だけの問題なのでしょうか。
端的にいえば“否”であると筆者は断言します。
スーパーマーケットなどの小売業において、POSレジなどから収集する売上を追いかける「売上至上主義」は遠い過去であり、現時点では営業利益を重視しています。
いうまでもなく、営業利益は荒利(売上総利益)から経費(販売費および一般管理費)を減じた結果なので、営業利益を獲得するには、荒利益率と荒利益額の確保が必須です。
他業態に比べて多品種少量を扱うスーパーマーケットは荒利を分析するために売価管理が必須であり、売価管理を突き詰めるには売価での棚卸が必要なので、結果的に在庫評価法は売価還元法になるのです。
このスーパーマーケットにとって必要不可欠な、売価還元法について解説します。
売価還元法とは
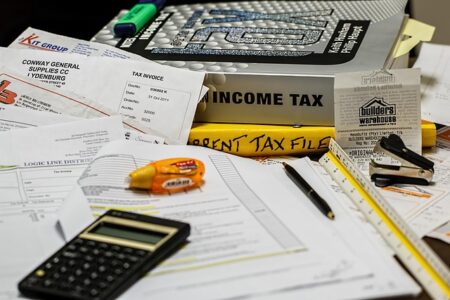
会計において売上総利益(荒利)は売上から売上原価を減じて算出し、売上原価は「期中総投入額(期首原価在庫高と期中原価仕入高の和)から期末原価在庫高を減じて算出」します。
つまり、期末原価在庫高は在庫を原価で評価するのであり、在庫評価法としては個別原価法、先入先出法、平均法、最終仕入原価法などがあります。
これらは全て、個々の在庫を原価で評価して数量を乗じて集計します。
対して、売価還元法の期末原価在庫高は「在庫を売価で評価して集計した期末売価在庫高に原価率を乗じて期末原価在庫高を算出」する、いい替えれば商品仕入時点の原単価に値入(原価に“もうけ”を加算する)して売価値付けした売価在庫高を原価に「還元(根源的な価格に再び戻す)」するのです。
この原価率は「期首原価在庫高と期中原価仕入高の和を期首売価在庫高と期中原価仕入高と原始値入高と期中値上高の和から値上取消高を減じた結果で除した数値」(連続意見書第4の売価還元低価法)をいいます。
なお、後述する不明ロスを反映させる目的で、「期首原価在庫高と期中原価仕入高の和を期中売上高と期末売価在庫高の和で除して算出」した数値を原価率にする方式(税法基準の売価還元法)もあります。
長年にわたりスーパーマーケットの部門別管理に携わってきた筆者としては、不明ロスを反映する後者を用いるのが良いと思いますが、上場企業等の中堅以上のスーパーマーケットは連続意見書に従わなければなりません。
【関連】不明ロスの原因と事例。原因を把握して利益管理を強化したい
参考計算式
小売業における計数管理に参考となる計算式の一例をご紹介します。
荒利額=売上額×荒利率
荒利率≒値入率+売価変更率-ロス率
前回期間ロス=(月次更新時に)-在庫修正
今回ロス=今回期間ロス+在庫修正
帳簿在庫=期首在庫売価+総仕入売価-売上+売変+在庫修正
推定ロス高=期間売上高×推定ロス率
帳簿在庫=期首在庫売価+総仕入売価-売上+売変+在庫修正-推定ロス
売買差益率=(売上-総仕入原価)÷ 売上
在庫増減高=総仕入売価-売上
詳細は「利益を生む!小売業のための 「計数管理 実践ガイド」」で解説していますので、そちらをダウンロードくださいませ。
売価還元法の計算式には表れない重要な数値

前段で、売価還元法は在庫を売価で評価する稀な方法であると解説しました。
スーパーマーケットが日本で普及した頃は、現在の様な安価で使いやすいITやネットワークはないので、棚卸実施時に在庫舗大半を占める店頭在庫の売価記入は容易でしたが、原価は担当者が過去の取引実績(主に仕入伝票)を調査して記入しなければなりませんでした。
原価記入業務は、多大な人時数が必要でしたので自ずと売価棚卸に傾斜しました。
しかし、ITやネットワークが高度に進化した昨今において、棚卸を原価で実施するのは売価で行うのと同程度でありながら、売価還元法と売価棚卸を継続している主な理由が2つあります。
1つ目は、棚卸を実施せずとも荒利を計算できるという理由です。
荒利額を算出するには期末原価在庫高が必要ですが、売価還元法を採用していれば、期末売価在庫高の理論値を計算で求められます。
理論(“帳簿”と表現するケースがある)期末売価在庫高は「期首売価在庫高と期中売価仕入高の和に売価変更額(値上額から値下と見切と廃棄の合計を減じた額)を加算し売上高を減算」します。
この在庫高にはロス(後述)分は含まれないので留意しなければなりませんが、概算値として利用するには支障がないと考えられています。
2つ目は、荒利額の構成要素には原始値入額と売価変更額(値上、値下、見切、廃棄)そしてロス額があり、スーパーマーケットが荒利額の出来不出来の原因分析に不可欠な各構成要素の検討が売価還元法では可能になるからです。
ロス額は先述した理論期末売価在庫高と実際に棚卸を行った期末売価在庫高との差額であり、ロス原因は原始値入のミスや売価変更額の計上ミスと社内外の不正行為(従業員の抜き取りや来店者の万引き)と考えられています。
この構成要素は、売価還元法を行う際の売価管理を行わないと把握できないのです。
売価還元法の儲かる仕組みの事例

ピーター・ファーディナンド・ドラッカー氏が著書「マネジメント」で提唱した『目標管理』は、企業の成長に多大な貢献をしました。
スーパーマーケットでも目標管理(MBO)を採用して“儲かる”(✖儲ける)仕組みを構築した事例は枚挙に暇はありませんが、失敗した事例も少なからずあります。
違いの一つは目標の立て方が具体的かつ定量的かどうかです。
成功事例は、荒利とともに構成要素である値入、売価変更=値下や廃棄、ロスの金額と売上対比率を目標としたのに対して、失敗事例は、荒利の金額と売上対比率のみで定量的ではあるのですが具体性は前者に劣り、“儲かる”レベルに達しなかったと推察します。
チェーンストアの経営スローガンに『3S主義』があり、その一つがsimplification=単純化です。
スーパーマーケットは荒利の課題について構成要素に分解して分析を “単純化”します。
目標設定は業務や数値に長けたスペシャリストが合理的な判断で行います。
そうすれば、ワーカーは容易に現状認識と改善行為の答えを容易に認識できます。
荒利が思う様に獲得できないスーパーマーケットでは、管理者が「値引や廃棄が多いのが原因である」と分析し、「目を皿のようにして現場を監視していました」けれども数値は改善しませんでした。
そこで、在庫評価法を最終仕入原価法から売価還元法に切り替え、構成要素を数値化するように助言すると“原始値入”が妥当な値では無かった実態が明らかになりました。
このスーパーマーケットの目標数値は荒利のみでしたので、担当者は管理者から「値引と廃棄に注意」するようにとの指示に従っていたに過ぎず、懸命に努力をしても荒利目標を達成できない状態が続いていたのです。
しかし、目標の設定を荒利以外に原始値入、売価変更(値上、値下、見切、廃棄)を設定し予実管理を行ったところ見事に荒利目標が達成できるようになったのです。
結婚式でよく使われるスピーチの『人生3つの坂=上り坂、下り坂、まさか』ではありませんが、スーパーマーケットでも少なからず発生する『まさか』の一つです。
まさか原始値入が低いとは夢にも思ってもいないのです。
スーパーマーケットは売価変更やロスの一定額を見込んだ原始値入を管理するのが“儲かる”仕組みづくりの原点であると断言できます。
【関連】基幹システムを通じたマーチャンダイジング実行に儲かるヒントがある
まとめ
ここまでは、説明が複雑になるのを避けるために、売価還元法とセットで利用する部門別管理の説明を省いてきましたが、スーパーマーケットの儲けとは店部門別の営業利益集計値です。
日本のスーパーマーケットが店舗を増加してチェーンストア化を推し進めても儲からず、米国のチェーンストアが儲かっているのは、米国では利益管理経営を行っているからだと言われます。
日本の部門別管理は売上をフォーカスし、荒利や営業利益を疎かにしているからなのです。
「当社では荒利や営業利益の管理を行っている。」と反論を受けるのですが、商品作業を常に見直して部門の経費低減を行っているのでしょうか。
部門の営業利益とは部門の荒利から部門の直接費と間接費を減じた結果です。
部門の直接費が店舗における部門の商品作業コストであり、間接費は商品部の商品作業と物流作業コストです。
部門別管理では、営業利益が赤字の店・部門を発見するのを目的とします。
米国のチェーンストアは巨大な黒字部門を持つのではなく、赤字部門が少ないから儲かっているのであり、日本のスーパーマーケットも赤字部門の商品作業力を高めて黒字化すれば儲かるようになります。
テスクが提供している小売業向け基幹システム『CHAINS Z』は、スーパーマーケットにおける豊富な導入実績を通じて、売価還元法や荒利、売価変更、ロスに関する長年にわたり培われた深い知見を持ちます。
小売業向け基幹システム『CHAINS Z』を利用すれば儲かるノウハウを獲得できます。
他にも、スーパーマーケット特化のスマホ販促アプリ「Safri」、バイヤー向け商談管理システム「商談.net」、小売業向け「リベート管理システム」を提供しています。
著者:株式会社テスク
愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企業様に導入されており、これまでに蓄積したノウハウを活かして、流通業の業務改善や経営課題の解決を支援しています。

