小売業の深刻な現状課題とは?DXを活用した解決策事例とともに紹介
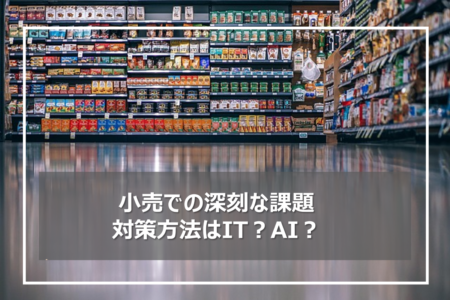
現代社会は、小売業にお構いなく、構造を大きく変化させています。
例えば、1990年の世帯主平均は40代であったのが、2040年には60代になる世帯主の高齢化、女性の非労働者の家事従事者と就業者の比率は1:1.5が1:2になり昭和時代の来店主体であった専業主婦の減少、平均構成人員は3人強から2人強になった統計が示す4人家族というモデルの崩壊、そして、20%から35%に代わった単身世帯比率の増加などは、小売業の戦略変更を示唆するデータです。
「そんなことは言われなくても解っている。」「だから新たな扱い商品や各種新サービスを売り場展開している。」と言った声を聴きますが、未だ不十分であると筆者が思い至る理由は、近視眼的な“稼ぐ”や“削る”にのめり込み過ぎ、“防ぐ”つまり中長期的なリスクに油断なく備え、先手を打っているようには見えないからです。
小売業をシステム面から40余年見続けてきた知見で、小売業が認識すべき課題と解決策の糸口を解説します。
目次
小売業の課題:他業界に比べて深刻な人手不足

日本の人口は、今後100年間で100年前に戻っていき、この変化は千年単位で類を見ない極めて急激な減少と言われています。
人口の急激な減少は、日本社会の随所に影響がありますが、低い人時生産性に因る低賃金から抜けられない小売業にとって最も深刻なのは人手不足として既に現れています。
そして、人手不足を助長しているのが定着率の短さです。
フルタイムにせよパートタイムにせよ、OFF-JTの後のOJTを経て一定の戦力として期待していた矢先に辞められると大きな痛手になります。
関連して大きな課題になっているのは、経験により培われたベテラン社員の知識とノウハウの伝承です。
個人商店からチェーンストアになり、企業として系統だった教育と豊富な経験を持つ社員が定年を迎え、現在は再雇用で延長していますが、限界に近づいています。
成長を支えてきた中堅社員からの知見の継承に猶予はありません。
小売業の深刻な人手不足、低い定着率、進まない知見の継承への方略は、マニュアル化とシステム化を主体とした教育時間の短縮と属人化からの脱却です。
DXやAIを話題にするケースでは、ITにフォーカスを当てる傾向が強いのですが、マニュアルの整備こそが重要なのです。
DXやAIは言い替えれば『便利な道具』ですので、道具を上手に使って「誰もが短時間で同じ結果」を出せるマニュアルが必要です。
マニュアル化を進め便利な道具を上手に使いこなせば、初心者と熟練者が均質化するまでの時間が短縮できます。
一方で、マニュアルは“心を込めたサービス”を妨害し、冷たい接客がお客の支持を失うと反対する意見が有ります。
しかし、個人技を放置すると過剰なサービスが横行し、オペレーションコストが膨れてしまう事例を少なからず見ています。
マニュアルにより、習熟が短時間で可能になり、業務遂行が能力から習慣に変われば、業務の余裕が「心を乗せる余裕」になります。
その上、余裕のある勤務は定着率の向上にもつながります。
マニュアルが進化し作業が効率化すれば労働生産性が高まり、少人数で店舗の運営が可能になるので、人手不足解消の一助になります。
また、高レベルの知見が組み込まれたマニュアルは、ベテランのスキル伝承にも役立ちます。
小売業の課題:競合店との競争とオーバーストア化

2000年の大店立地法施行に伴い、旧来の個人商店とチェーンストアの競合から一定規模以上のチェーンストア間の競合に変わりました。
業種店のマーケットシェアを業態店が品揃えと低価格で簒奪し、業種店が淘汰されて店舗数は減りました。
しかし、規模や価格が同質化したチェーンストア店舗同士が食い合うと言ったゲームにチェンジした後は、店舗が淘汰されずに増え続け、商圏内の適正な店舗数を超えて乱立するといった状況=オーバーストア化になりました。
小売業の店舗売上は、ハフモデルの様に距離と売場面積等の魅力度に影響を受けるとされています。
つまり、消費者の来店動機は主に距離に影響を受けるのですが、小売業の出店が過密化しているので、旧来の対象商圏が縮小して店舗の売上が縮小し、立地によっては損益分岐点を下回っています。
オーバーストアにより激化した競合で優位の立つためには、ディスカウントを消費者に印象付けます。
しかし、全品が競合する店の中で最低である必要はなく、自店が扱う地域の生活必需品は競合店よりも安くして低価格イメージをアピールすると同時に、高価格イメージを抱かせないために高価格商品を扱わずに、狭い価格レンジに限定します。
さらに、主たる商圏の縮小による客数減少には、対象にする顧客層を広げつつ、購買頻度の高い商品の品揃えを厚くして、来店頻度の上昇に因る客数増加を計画します。
この際に決して疎かにしてはならないのが、自動発注システム等を利用した、売れている商品の売り場欠品防止です。
小売業の課題:消費者心理の多様な変化

小売業の本部事務所を訪問すると、まれに『現場主義』や『現場密着』との額装が掲げられていますが、筆者は常に違和感を持ちます。
正に耳障りは良いのですが、『現場主義』は『その場主義』と翻訳できます。
ECやネットスーパー、ピックアップ・デリバリーなどの販売と売渡方法が多様化し、それらニーズに対応するフォーマットが出現している環境において、『現場主義=その場凌ぎ』ではフォーマット間競争に勝てません。
多種の消費者行動を良く観察した上の予測を行い、新しいフォーマット開発の必要性を感じます。
過去に「ニューフォーマット」にチャレンジした事例を振り返ると、物理的規模の拡大=売場面積を広げて高額な商品と低い購買頻度の品揃えを行って高くて古いイメージをお客に持たれてしまった事例を思い出します。
この間違いを反省したニューフォーマットは、お客が売り場やECサイトで常に新たな発見を感じ、来訪したくなる店舗やサイトでなければなりません。
それには、現時点の品揃えを見直しが必要です。
つまり、品種内の重複品目を廃し、空いたスペースに新たな品種を加えるのです。
その際に留意すべきは、『ペットボトル飲料』や『フローズン』の様に、自社と同一の高収益フォーマットや集客している他フォーマットの品種商品でなければなりませんし、欧米の成長しているチェーンストアを見学し、品揃えを正しく模倣するのも忘れてはなりません。
だからと言って店舗の作業種類を増やし、セルフサービスの完全化を疎かにしてはローコストオペレーションが後退してしまいます。
人海戦術を廃して機械化やデジタル化と言った新たなテクノロジーを積極的に採用し、物流センターや加工センターの機能を拡大し、店舗後方作業を合理化し、ディスカウンティングの前提条件であるローコストオペレーションを追求し続けます。
ストアコンパリゾンで得た知見をライン・ロビングに生かし、更なるディスカウンティングを追求した結果として、ニューフォーマットが出来上がります。
小売DX化に成功した事例:システム化や自動化の整備遅れへアプローチ
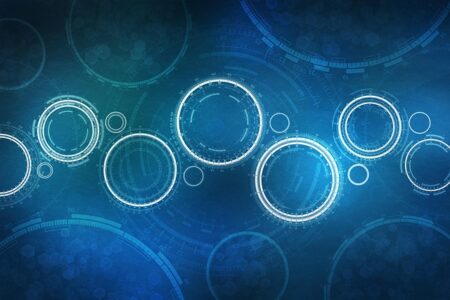
小売業は流通業の中でも作業や工程の分析と再構成が遅れており、店舗や本部の作業や業務が重複しているので、店舗の作業をセンター等に集約して大胆に削減する必要に迫られています。
店舗も本部も業務や作業手順と方法を、マニュアルの整備を通じた規格化で、コスト低減やビギナーとベテランが短期間で平準化するように努めます。
そして、これらの推進に貢献するのがシステム化と自動化整備です。
小売業におけるシステム化と自動化の適用分野は多岐にわたりますが、次の分野からの着手が成功事例も豊富なので失敗確率が低い様です。
事例1:ECサイト
ネットスーパーサービスは、物流システムを自社で実施しなければ赤字になる確率が高いので、自社物流システム構築までを考慮したくなりますが、プロジェクト規模もコストもリスクも高くなります。
しかし、宅配便配送を前提とした商品販売や中元・歳暮、おせちなどのECサイト販売であれば、導入するコスト=リスクは低いので導入が容易になります。
また、自社特有の人気商品を持ち、毎年の売上が一定以上あれば、チャンスロスの減少を通じた売上増加や、ペーパーレスによる作業種類数の大幅な削減が期待できます。
【参考】基幹システムとEC・通販サイトの関係性とは?システムとの連携について解説!
事例2:スマホアプリによる販促
DXの起爆剤になったスマートフォンの普及は今後もしばらく継続すると推測できます。
若年層や現役世代のみならず、引退世代にも普及し、全世代の情報収集媒体がスマートフォンにシフトします。
その結果、新聞購読者数が年々激減し、小売業の販促媒体の主役であった新聞広告や折込チラシは効果が薄れてきています。
この際には、スーパーマーケット特化のスマホ販促アプリ「Safri」など活用した販促・顧客囲い込みが効果的です。
【参考】これからの販促にアプリが効果的な理由とは?新しい販促企画をご紹介
事例3:自動発注
自動発注は、小売業にも多数導入されているので、今や導入を検討する段階では無く、数ある方式からカテゴリーごとに適切な方式を選択する段階になっています。
また、AIを使った精度の高い自動発注事例も見聞きするようになっていますが、AIを導入することが目的ではありません。
精度の高い自動発注を実現して発注工数を削減することが目的なので、稼働実績が豊富な自動発注システムを使い、段階的にAIによる需要予測型の自動発注システムへの切り替えが成功への近道です。
事例4:バイヤーの商談業務を効率化
小売業においてWebを使ったオンライン商談は珍しくなくなりましたが、対面商談に比べた小売業側労働生産性向上効果は皆無に近いです。
そこで、小売業商品部メンバーが一斉に卸・メーカーに対して提案依頼を行い、Web上で提案内容・条件を評価し、卸・メーカーに競争してもらってから採用提案を決めます。
採用した商品情報を社内システムに連携させる商談管理システム「商談.net」を使えば、個々に属人化した商談方法が合理化され、商談業務の工数削減、仕入原価低減に繋がります。
事例5:リベート管理
お取引先(卸やメーカー)からは、少なくないリベートを頂いていますが、荷姿型や達成型を問わず、小売業は企業として管理していません。
商品部の担当者がEXCELを使って、個人的に入金との照合をしているか、入金額をそのまま受け入れる場合が大半です。
リベート計算方法は複雑であり、システム化し難い分野ですので、「管理してもリベート額が増えるわけでもないので、システム投資は経済性を担保しない。」と諦めて取り組まないのです。
しかし、小売業向け「リベート管理システム」を導入した企業の事例では、特に達成型リベートを成り行きから科学的管理に切り替え、システム投資額の数倍が単年度で増額し、その後も継続しています。
事例6:従業員教育
スマートフォンが普及していない頃の従業員教育は、店舗のパソコンに登録されている教育ソフトや動画を利用していました。
現在は、無線LANやWi-Fi等の高速ネットワーク社内外に設置され、さらに充実した機能を持つ安価なE-learningや動画・マニュアル作成ソフトのサービスが利用できます。
その上、場所や時間に制約があるパソコンではなく、業務に携わる皆さんがお持ちのスマートフォンで安価で充実した機能の動画を活用すれば、従業員教育は非常に取り組みやすくなります。
【参考】スーパーマーケットにおける教育目的とエンゲージメントを考える
まとめ
テスクは、創業以来流通業に特化したシステム化を通じて小売業様や卸売業様の御繁栄に貢献しています。
特に、小売業様には業務の効率化を短期間で実現する小売業向け基幹システム「CHAINS Z」、商談に絡む一連の業務・作業手順と方法を規格化して商談を革新するバイヤー向け商談管理システム「商談.net」、人海戦術では実現しえなかったリベート管理をシステム化して受け身の姿勢から脱却する小売業向け「リベート管理システム」などの豊富な成功事例を持つソリューション群を運用マニュアル付きで提供しています。
著者:株式会社テスク
愛知県名古屋市に本社を構え、1974年から流通業向け業務システムの構築に特化してきたシステムベンダーです。小売業向け基幹システム「CHAINS」は400社以上、卸売業向け販売管理システムは200社以上の企業様に導入されており、これまでに蓄積したノウハウを活かして、流通業の業務改善や経営課題の解決を支援しています。

