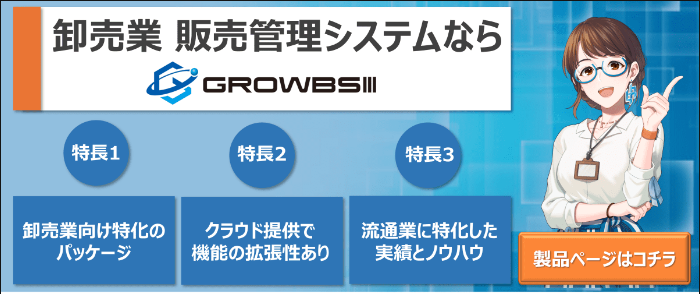中堅卸売業の生き残り戦略ーー地域密着と業務改革で未来を切り拓く
元セントラルフォレストグループ株式会社・株式会社トーカン 専務取締役 神谷氏インタビュー

人手不足・原価高・物流コスト高騰・大手企業のM&Aなど、いま、中堅卸売業はかつてないほどの構造的課題に直面しています。
しかし一方で、「地域密着力」「業務改善力」「IT・DXの活用」によって、大手には真似できない生き残りの道を歩む企業も増えています。
本記事では、元セントラルフォレストグループ株式会社・株式会社トーカンの専務取締役であり、長年卸売業の経営・改革に取り組まれた神谷氏へのインタビューをもとに、中堅卸が生き残るための実践的戦略を紹介します。

中堅卸売業の課題・現状を取り巻く環境とは

中堅卸売業が直面しているのは、単なる「人が足りない」「コストが上がっている」といった表面的な問題ではありません。
構造的な課題が複雑に絡み合い、従来のやり方では収益を確保しづらくなっています。
ここでは、神谷氏が語る”中堅卸売業の4つの課題”を紹介します。
1. 深刻化する人手不足と人件費の上昇
中堅卸売業では、少子高齢化や労働環境の厳しさを背景に人材不足が常態化しています。
単に人数が足りないだけでなく、倉庫・配送・営業など各部門で即戦力となる人材の確保が難しいのが現状です。
採用競争の激化により賃金水準を引き上げざるを得ず、人件費が経営を圧迫しています。
限られた人員で業務を回すには、効率化と人材育成の両立が欠かせません。
2. 仕入れ価格・物流コストの高騰
原料高や円安に起因するメーカーの値上げが相次ぎ、仕入れコストが増加しています。
さらに「2024年問題」など法改正の影響でトラック運賃も上昇し、物流費が大きな負担になっています。
仕入れ・物流・人件費の三重コスト増が進む中で、従来の利益構造では吸収しきれない状況が続いています。
3. 価格転嫁の難しさ
地域の小売業や飲食店を取引先とする中堅卸では、価格転嫁が進みにくいのが現実です。
販売価格を上げれば取引が減少するリスクがあり、大手チェーン相手でも交渉力の差から値上げが難しい場合があります。
結果として、上昇したコストの多くを自社で負担することになり、利益率が低下しています。
4. 全国チェーン化による顧客基盤の変化
小売業界のM&Aが進み、地域スーパーや専門店が全国チェーンに吸収される動きが加速しています。
これにより、地元を中心に取引してきた中堅卸は商流の再編に直面し、取引機会を失うケースも増えています。
一方で、地域の食文化や消費者ニーズを理解した地場密着型の卸には、独自の存在価値が残されています。
中堅卸売業の生き残りの戦略・課題解決に向けたアクション

このような厳しい環境の中でも、地域に根ざした中堅卸には確かな活路があります。
神谷氏は「大手と同じ土俵で戦わず、自社の強みを徹底的に磨くこと」が重要だと語ります。
ここからは、中堅卸が生き残るための具体的な戦略を4つの視点から見ていきます。
1. 地域密着を最大の武器にする
食品は地域性の強い商材です。味噌、調味料、惣菜、地元メーカーの商品など、地域ごとに嗜好が異なります。
長年その土地で商いをしてきた卸だからこそ、地元の消費者と小売をつなぐ「橋渡し役」になれるのです。
地域性を理解した商品提案や販売支援こそ、中堅卸の最大の強みといえます。
2. “非効率”を効率的にこなす
中堅卸のもう一つの価値は、大手が避ける非効率な業務を、効率的に回す力です。
小口・多頻度配送、地域密着の対応などは一見非効率に見えますが、業務設計とITの活用次第で高収益モデルに変えることが可能です。
業務の効率化によって「小さいけれど強い」卸を目指すことが求められます。
3. 改善活動による業務改革と人材育成
神谷氏は、現場からの改善活動が経営の柱になると強調します。
物流・事務・営業といった全領域で改善を行うことで、以下が同時に進みます。
- 生産性の向上
- 組織内コミュニケーションの活性化
- 人材育成・意識改革
「改善活動は人を減らす取り組みではなく、人を成長させる取り組み。これが結果として会社を強くする」と神谷氏は語ります。
4. 共同物流・連携によるコスト削減
単独での物流維持は難しい時代です。
複数の企業で配送ルートや倉庫を共有する“共同物流”により、コストと環境負荷を同時に削減できます。
神谷氏は「業界全体での共同化こそが持続可能な経営の鍵」と語ります。
中堅卸売業は、その中心的プレイヤーとしての役割を果たすべき時期に来ているでしょう。
中堅卸売業のDX化・システム投資について
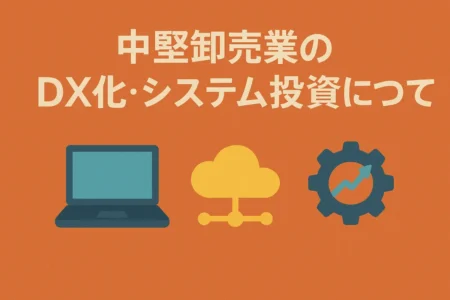
課題解決と業務効率化を進めるうえで、システム投資は避けて通れません。
しかし、独自開発や過剰なカスタマイズは中堅卸にとってコスト負担が大きく、運用リスクにもつながります。
ここからは、神谷氏が語る“失敗しないDX化の考え方”を紹介します。
1. 独自開発より“パッケージ×クラウド”を選ぶ
神谷氏は次のように語ります。
「企業規模に関係なく必要なシステム機能は共通です。だからこそ、独自開発ではなく、パッケージやクラウドを活用するべきです。」
パッケージ型クラウドシステムは、導入スピードが早く、コストを抑えながら常に最新機能を利用できます。
中堅卸にとっては最も現実的で、効果的な選択肢といえるでしょう。
2. “業務を再設計してから”システムを導入する
「現行業務をそのままシステム化してはいけない」と神谷氏は強調します。
まず紙に業務を描き出し、重複やムダを洗い出して再設計する。
効率的な業務フローを構築した上でシステムを当てはめることで、長期的に陳腐化しにくい仕組みが実現します。
3. 提案型ベンダーとのパートナーシップ
ベンダー任せではなく、「提案型のパートナー」と連携することが成功の鍵です。
ユーザー側が受け身にならず、共に改善を進める体制を築くことで、DXの成果は大きく変わります。
4. 卸売業向け販売管理システム「GROWBSⅢ」による業務効率化の実現
神谷氏は、テスクが提供する卸売業向け販売管理システム「GROWBSⅢ」についても次のように評価しています。
「テスクさんのように、中堅卸の現場を深く理解して設計されたパッケージは非常に有効です。
独自開発にこだわらず、こうした実績ある仕組みを使うことで、業務効率を上げながらコストも抑えられます。」
「GROWBSⅢ」は、卸売業に特化して開発され、受発注・仕入・入荷・在庫管理・売掛・買掛・請求・支払・他システムとの連携など、卸売業に必要な機能が網羅されたクラウド型のパッケージシステムです。
“業務改善提案型ベンダー”として長年の実績を持つテスクは、中堅卸売業が目指すべきDXの実現を支援しています。
まとめ:中堅卸売業が未来へ生き残るために必要なこと
中堅卸売業が直面している人手不足、物流コストの高騰、価格転嫁の難しさ、これらは一時的な波ではなく、構造的な課題です。
しかし、課題があるということは、変革の余地があるということでもあります。
これからの時代に求められるのは、「大手と同じことをする」ではなく、「自社ならではの強みを磨く」戦い方です。
地域の特性を理解し、地場の小売業や飲食店とともに成長していく姿勢こそが、中堅卸売業の存在意義を際立たせます。
そのためには、長年培った現場力に加えて、業務改善とDXの力を融合させることが重要です。
業務をゼロベースで見直し、システムを単なる“ツール”ではなく、“業務を変革する仕組み”として活用すること。これにより、人材不足やコスト上昇といった課題を、成長の機会に変えることができます。
神谷氏が語ったように、独自開発や属人的なやり方ではなく、標準化された仕組みを柔軟に取り入れる発想が、持続可能な経営の鍵です。
業務のデジタル化を支えるツールの一つとして、卸売業向け販売管理システム「GROWBSⅢ」のような業界に特化したパッケージを活用することも有効でしょう。

■神谷 亨氏 経歴
1979年 株式会社トーカン 入社
2014年 同社取締役専務執行役員 管理統括部長就任
2019年 セントラルフォレストグループ株式会社専務取締役 経営統括本部管掌
2021年 三給株式会社 代表取締役会長 就任
2021年 株式会社ヒカリ 取締役会長 就任